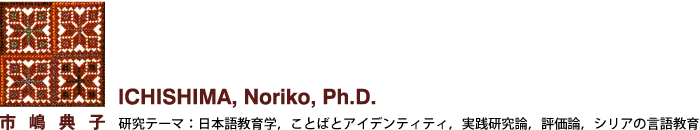更新情報・お知らせ
- 参加者募集 [2025-06-25]
 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業(中部ブロック・金沢)2025年度第1回研究会「学校教育×日本語教育―外国につながる子ども支援の可能性と課題」
日本語教師養成・研修推進拠点整備事業(中部ブロック・金沢)2025年度第1回研究会「学校教育×日本語教育―外国につながる子ども支援の可能性と課題」- 2025年7月13日(日)金沢大学(対面&オンライン)
- オンラインフォームから事前申し込みが必要です(7月10日締切)。
- 発表しました [2025-06-25]
- 大養協2025年度春季大会シンポジウム「各地域の日本語教育の現状・課題を踏まえた日本語教員養成課程のあり方を考える」
- 2025年6月15日(日)14:00~,(オンライン)
- 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業(中部ブロック)の活動として「外国人散在地域における日本語教育と日本語教員養成のあり方」を発表しました。
- 採択されました [2025-06-25]
- 市嶋典子(研究代表者)「能登地域におけるレジリエンス生成過程の検証と日本語教育支援連携モデルの構築」
- JSPS科研費(基盤C,25K04208)[科研費データベース]
- 発表しました [2025-06-24]
 CHEERS主催『ことばと公共性―言語教育からことばの活動へ』読書会(テラコワ,名古屋)2025年4月20日[チラシ]
CHEERS主催『ことばと公共性―言語教育からことばの活動へ』読書会(テラコワ,名古屋)2025年4月20日[チラシ]- 2章 コロナ禍における留学生交流事業の取り組み―「第三の故郷を見つける農家民泊」再開までの軌跡
- 開催しました [2024-10-24]
 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業(中部ブロック・金沢)2024年度シンポジウム
日本語教師養成・研修推進拠点整備事業(中部ブロック・金沢)2024年度シンポジウム- 2024年11月4日(月・振休)14:00~,金沢大学にて開催(オンライン参加可)
- オンラインフォームから事前申し込みが必要です(10月30日締切)。
- 執筆しました [2024-10-24]
- 市嶋典子(2024).コロナ禍における留学生交流事業の取り組み ― 「第三の故郷を見つける農家民泊」再開までの軌跡.牛窪隆太,福村真紀子,細川英雄(編)『ことばと公共性 ― 言語教育からことばの活動へ』(pp. 52-70)明石書店.
- 書評情報 [2024-10-04]
 マリオッティ,M.,市嶋典子(2022).細川英雄(監修)『「活動型」日本語クラスの実践 ― 教える・教わる関係からの解放』スリーエーネットワーク.
マリオッティ,M.,市嶋典子(2022).細川英雄(監修)『「活動型」日本語クラスの実践 ― 教える・教わる関係からの解放』スリーエーネットワーク.- 工藤理恵,武一美(2024).【書評】細川英雄監修 マルチェッラ マリオッティ・市嶋典子著 「活動型」日本語クラスの実践 教える・教わる関係からの解放『早稲田日本語教育学』35,173-177.http://hdl.handle.net/2065/0002000824
- 『新英語教育』2023年5月(645号) Book Review『「活動型」日本語クラスの実践』
- 発表しました [2024-09-02]
- 佐藤慎司,市嶋典子,宇佐美洋,熊谷由里,南浦涼介(2024年8月1日).「日本語教育における「評価」活動を考えるー学習者、教員、社会の評価・価値・価値観をめぐって」ICJLE 2024 日本語教育国際研究大会(ウィスコンシン大学マディソン校).
- 発表しました [2024-07-21]
 日本語学習者が語るライフストーリーからことばの学びを捉えなおす ― 個の語りからせまるシティズンシップ(講師:市嶋典子)
日本語学習者が語るライフストーリーからことばの学びを捉えなおす ― 個の語りからせまるシティズンシップ(講師:市嶋典子)- 2024年7月21日(日)9:30~11:30
- 対面(リファーレ金沢・4F大研修室)およびオンライン
- (公財)石川県国際交流協会主催『石川県の外国人住民との共生を考える講座』第1回
- こちらのオンラインフォームから事前申し込みが必要です。
- 発表しました [2024-06-29]
 文科省 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業 2024年度第1回研究会「実践をひらく」
文科省 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業 2024年度第1回研究会「実践をひらく」- 2024年6月29日(土)14:00~16:00
- 対面(金沢大学)およびオンライン
- 事前申し込みが必要です。
- 日本語教育実践を研究し共有することの意味/市嶋典子(金沢大学 教授),ほか
- 開催しました [2024-03-15]
 文化庁「日本語教師養成・研修推進拠点整備事業」中部ブロック スタートアップシンポジウム
文化庁「日本語教師養成・研修推進拠点整備事業」中部ブロック スタートアップシンポジウム- 2024年3月23日(土)13:30~17:00(ホテル金沢)[参加申し込み:3月20日締切]
- 基調講演:今村聡子(文化庁国語課長)「日本語教育機関認定法の施行について」
- 基調講演:細川英雄(早稲田大学名誉教授)「対話とコミュニティ ― 日本語教育の専門性をつくるもの」
- 発表しました
- 「非営利型一般社団法人 日本語まなびサポート北陸」設立記念講演会&座談会
- 2024年3月10日(日)13:30~15:30(石川県政記念しいのき迎賓館)
- 基調講演:市嶋典子「彼/彼女らはなぜ日本語を学び続けるのか ― シリア難民アリの場合から」[チラシ]・[参加申し込み]
- 金沢大学は、2023年9月29日付けで、文化庁「日本語教師養成・研究推進拠点整備事業」(中部ブロック)に採択されました。 [2024-01-30]
- 執筆しました [2023-06-01]
- 市嶋典子(2023).「シティズンシップとことばの学び――シリア出身の日本語学習者の語りから」佐藤慎司,神吉宇一,奥野由紀子,三輪聖(編)『ことばの教育と平和――争い・隔たり・不公正を乗り越えるための理論と実践』(pp. 33-60)明石書店.
- 発表しました [2023-04-01]
- 市嶋典子(2023年3月11日).「第三の故郷を見つける農家民泊」(オンライン講演)秋田市主催育む活動報告イベント『誰かと共に育むこと』(秋田市文化創造館)https://akitacc.jp/event-project/park_0311/.
- さらに過去のお知らせ
研究内容
研究テーマ:日本語教育学,ことばとアイデンティティ,実践研究論,評価論,シリアの言語教育
日本語教育学における実践研究や、国内外の日本語学習者・教師へのライフストーリー調査をもとにした研究を行ってきました。また、移民や難民の言語意識や、シティズンシップ、アイデンティティ研究にも関心をもち、研究をとおして、なぜ人はことばを学ぶのかという問いを考察しています。日本語教育学の知見から、外国籍の人々が直面している問題を考察し、多文化共生社会を実現するための理念と方法を模索していきたいと考えています。
現職
- 金沢大学 人間社会研究域国際学系 教授
- 筑波大学 地中海・北アフリカ研究センター 客員共同研究員(人文社会科学部門)